
海幸山幸彦の解説編です
今回はいよいよ日本神話「海幸彦山幸彦」の解説編をやっていきたいと思います。
「え?まだ読んでないけど?」
というあなたは、まずは前編と後編のほうを読んでおいてください。


前編の時にも少しお話したように、神話「海幸彦山幸彦」には人生の試練(壁)を乗り越えるためのヒントが隠されています。
それはこのお話の中に、人間の本質的な「型」が示されているからなんですね。
神話というのはただのおとぎ話ではなくて、そこには人間の本質的な濃い情報、もっと言えば人生の設計図が見えてきます。
なので神話の本当の意味を知ることで、その濃い情報が自分の中にインストールされ人生における視野(視点)が広がります。
(別の言葉で言えば「次元」を上げることになります。)
視野が広がれば(次元が上がれば)、知らない時よりもより良い人生を歩みやすくなります。
そしてこのお話のメインテーマになるのが、「アイデンティティクライシス」です。
(´_ゝ`) アイなんて?
「アイデンティティクライシス」とは文字通り自分の持っている価値観の崩壊という意味なんですが、以前このブログでもお話した「人生の4つのステージ」で、今のステージより上のステージにいくためには(次元を上げるには)、このアイデンティティクライシスが必要になるんですね。
→人生のステージ(魂レベル)にある4つの段階と高い人低い人の特徴
これはステージを上げるための試練ともいえるし、また別の言葉を使えば人生における壁(試練)を乗り越えるために必要な痛みとも言えます。
「卵は世界だ」という言葉もあるように、次の世界に行くためには殻を壊す必要があります。
この殻というのが、今までの自分自身の持っている価値観です。
このアイデンティティクライシスの前後は、世の中的には損をする事が起こる場合もありますが、それは「損して得をとれ」という言葉もあるように、その時は損と感じるかもしれませんが、人生全体という長い視点から見れば結果的に得をすることになります。
なのでこのアイデンティティクライシスの仕組みを知っておくだけでも、今後の人生にとって無駄はないです。
というわけで、いつも通り少し前置きが長くなりましたが、笑 さっそく日本神話「海幸彦山幸彦」の解説編いってみましょう。
最初は「うらやましい」から始まる
物語の冒頭、海幸彦と山幸彦はそれぞれの場所で平和に暮らしていました。
そして弟の山幸彦が兄の海幸彦に対して、
「うらやましいな~。」
という気持ちが現れることで物語が動き始めました。
「よその芝生は青く見える」
という言葉があるように、人間というのは自分にないものに憧れ、うらやましいという感情は大なり小なりみんな心の奥底にあります。
この物語での釣り針というのは、「自分にないもの」の象徴です。
そして物語の中で山幸彦は兄の大事な釣り針をなくし、それをなんとかしようとします。
これはさっき言った、「自分にないもの」をなんとか手に入れようとする状態です。
山幸彦は釣り針を500個作り→ダメだった→1,000個と作りました。
人に対しての憧れから始まり、自分にないものを手に入れるために、
「よし!あれをやってみよう!」
「でもダメだった、、じゃあこれもやってみよう!」
と今の自分にできる事を全部やって、もがいている状態です。
これは人生の中での足し算の時期と言って、
「若いときの苦労は買ってでもしろ」
という言葉もあるように、この時期はとにかくがむしゃらに自分のやれることをいろいろとやりまくります。
そして物語の山幸彦のようにそれでも上手くいかない。
「あれだけ努力したのに全部無駄だった、、」
と人生に絶望して落ち込みます。
この足し算の時期は、その時は「無駄だった」と感じてしまいます。
でも実はこの足し算は人生においてとても大事な時期で、ここでやったことや絶望したマイナスのエネルギーは、その後の人生で「再定義」をする事によって、マイナスが大きければ大きいほどプラスのエネルギーになって還ってきます。
→過去を変える方法はあるのか?人生の後悔やトラウマを乗り越える考え方
エネルギーというのは宇宙的な視点から見ればプラスもマイナスも同じで、そのエネルギーを自分の中で「どう定義するのか?」で敵にも味方にもなります。
「人生に無駄なことはない」
という言葉もそういう視点から見ています。
そして物語では足し算をやりつくし、絶望(負のエネルギー)を手に入れた山幸彦の前に謎の老人が現れます。
この謎の老人とは「人生の道しるべ」の象徴です。
別の言葉では、メンターや指導者になります。
これは人生を変えるきっかけになる人や出来事です。
指導者と言っても別に師匠とかそういう人限定ではなくて、それは友人やパートナー、仕事でのお客さん、尊敬している人、近所の人の何気ない一言だったりします。
それによってあなたの人生を変える、きっかけや気づきとなるものです。
人生を変えるきっかけは自分から向かうパターンもあれば、自分の意思とは関係なく訪れる事もあります。
(厳密には潜在意識の深い部分では求めていても、自分では気づいてないだけですが。笑)
物語の山幸彦の場合は、半ば強引に謎の老人に木の船に乗せられ、釣り針探しの旅に海へ出ます。
この場面の「海」は顕在意識を表しています。
顕在意識とは「表面的な自分」です。
海の上はいろいろな木の破片やゴミが浮かんでいます。
そしてこれらは自分の持っている悩みや不安などを表しています。
しばらくして山幸彦は海の中に潜っていきます。
これは「海の中」=「自分の中」です。
深く深く潜っていくほど、表面のゴミが影響しない本当の自分に近づいていきます。
竜宮城のような建物は「本当の自分」、また別の言葉で言えば、真我や御霊という場所になります。
ここまでの流れを少しまとめると、他人に憧れていろいろな事を試したけど、なにをやっても上手くいかない。
そんな時(絶望)にある人(メンター)との出会いによって、自分の中にある本当の自分の声を聞くことになります。
「本当の自分」が教えてくれたものとは?
竜宮城のような場所で山幸彦は3年という月日を過ごした後、こう思います。
「オレは一体ここに何しに来たんだ?」
「そうだ!なくしたアニキの大事な釣り針を探しに来たんだ!」
本当の自分の中で、人生において
「本当の自分はこの世に何をしにきたのか?」
という魂の願望を聞きます。
そして海の神わだつみにこう言われます。
「いいか山幸彦よ。これからお前の兄にこの釣り針を返す時、
心の中でこう思いなさい。」
「つまらない針。」
「貧しい針。」
「上手くいかない針。」
「どうでもいい針。」
これは今まで大事だと思っていた釣り針(自分にはないもの)は、実は自分にとって、
- つまらないもの
- 貧しいもの
- 上手くいかないもの
- どうでもいいもの
と本当の自分に教えられます。
今まで自分にとって大事だと思っていたもの(価値観)は、実は大事ではないもの(無価値)という事に気づくという事を意味しています。
(物語の中の山幸彦はこの時点で気づいてはないですけどね。)
この部分が「アイデンティティクライシス」=「今まで自分の価値観の崩壊」です。
そしてわだつみの「兄とは反対の事をしなさい」という言葉は、人生でステージを上げるためには今までの自分と同じ行動していては、ダメだという事を意味しています。
これはよく自己啓発系やスピリチュアル系でもある「常識を疑え!」というやつで、この常識という言葉は自分という言葉にも置き換える事ができますね。
もちろんこれも「どこまで?」という線引きのバランスもとても大事な部分で、今ある法律(ルール)をめちゃくちゃ無視して人様に迷惑かけるような事は言わずもがなです。
そしてわだつみにもらった2つの玉、潮満玉、潮干玉の意味は、「異なる2つのもの」、もう少しわかりやすく言えばこの世の陰と陽の「二元性」を表しています。
→二元性とは?スピリチュアルにもある話をわかりやすく説明します
これはどちらか片方があればいいのではなく、どちらも必要、「二つで一つ」という意味があります。
スピリチュアル系でもポジティブ、ネガティブという異なる二元性がありますがこれも、
「とにかくネガティブは悪い!」
というだけの視点はバランスが悪く、
「ネガティブがあるおかげでいろいろな気づきができる」
という別視点も必要です。
ここまでを簡単にまとめると、、
・他人への憧れから始まり、「自分以外のもの」になろうといろいろな事を試みる。
・いくら努力しても上手くいかず、人生に絶望し挫折をする。
そんな時メンターに出会い自分の向かうべき方向に気づかせてくれる。
・そして本当の自分の中(海の中)で答えを見つけ、「今までの自分の価値観」を壊し、今までの自分とは逆の行動をし、陰と陽を認めることによって一つ上のステージに行くことができる。
この海幸彦山幸彦は物語を通して、「人生における試練(壁)を乗り越えるヒント」を教えてくれる神話です。
日本は和の国
そしてこの神話のいいところは、最後は海幸彦と山幸彦は共に協力して生きていくという部分です。
海外の神話なんかだと、「ヒーロー(正義)が敵(悪)を倒す」という正義対悪の二元論で語られている場合が多いですが、日本はやはり和の国なので、いろいろな異なるものをまとめるという性質があります。
例えば料理でも日本では「和え物」という言葉もあるように、いろいろな異なる個性をひとつにまとめるという事が得意な人種なんですね。
そういった和の精神も、この海幸彦山幸彦という神話から伝わってきます。
最初の「前編」でもお話したように人生の試練(壁)というものは、実にいろいろなパターンがあります。
そしてそのパターンには型があると説明しました。
この神話「海幸彦山幸彦」の場合は、その中でもアイデンティティクライシス(それまでの価値観の崩壊)という型をテーマにしたお話です。
このアイデンティティクライシスは人間関係、仕事関係、夫婦関係、恋愛関係、親子関係、お金関係などあらゆる問題のパターンと関係しています。
なので最初にも言ったように、こうした型をインストール(知っている)するだけで、自分自身を少し俯瞰した視点で見られるようになり、今後そういった問題に対する対処の仕方も変わってきます。
この「俯瞰して物事を見れる」というのは、別の言葉で言えば「少し高い次元から見れる」と同じことなんですね。
まとめ
今回まで、計3回に渡りお伝えしたこの日本神話「海幸彦山幸彦」が、このブログを通して少しでも読んでくれた人の人生のヒントになればと思います。
日本神話についてはまた別の記事も書く予定なので、まあ期待はせず信頼しておいてください。笑
(´_ゝ`)ふ~ん
「お米の日本神話」についてはこちら。
→日本人にとって最もエネルギー的に効果のあるスーパーフードとは?
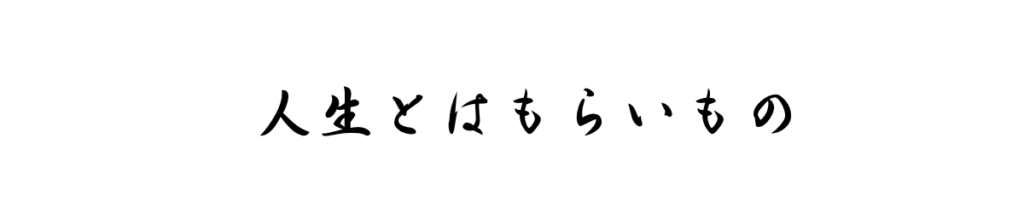
ノリさん、こんにちは✨
「日本神話に学ぶ~」三部作(?)読みました。
自分でも意外だったんですが、最初「海幸彦山幸彦」のお話だと聞いて、「あっ、知ってる…」と思ったんですが、よく考えてみると、オチを覚えていなかったんです(笑)
山幸彦が途方にくれるところくらいまでは覚えているんですけど…(^_^;)それもあって最後まで興味深く読めました。
古代から伝わっている神話の中にこんなメッセージが読みとれるなんておもしろいですね。
神話ではないのですが、昔話によくある大きいアイテムより小さいアイテム選んだり、イソップの金のおのと銀のおのなどもそうなんですけど、素直で欲がないとかえって得をしたりとかってスピリチュアル的な示唆をしてるのかなあ…とときどき思うことがありました。やっぱり実人生にはあんまり反映してないんですけど(笑)
よかったら、こうした昔話とか、ギリシャ神話なども、機会があったら読んでみたいです。「期待」しないで待っています(笑)(*^^*)
Mioさんコメントありがとうございます。
期待しないで待っててください。笑(^_^)
ノリさん、こんにちは!
読みまくらせていただいている、くみです。
数日にして、私の教祖様になってしまったノリさんです笑笑
でも、人間の本能?なのか、逆にこっちサイドが救世主みたいに教祖様を作り上げちゃうのって、あるかもしれませんね。
今回の神話、感動でした。最初の、羨ましい〜という隣の芝生も、別の視点では 笑 さらなる成長?ともとれますか。やる気というか、欲というか。
お金と欲について、いつか書いてくださると嬉しいです。もちろん人それぞれのバランスだとは思うのですが。正直、わかりません!
大切だとは思います。でも、どんなにお金持ちでも、どんどん欲が膨らんで、挙げ句の果てに逮捕、みたいなニュースたくさん 苦笑。
よろしくお願いいたします。
くみさんコメントありがとうございます。
「逆にこっちサイドが救世主みたいに教祖様を作り上げちゃうのって、あるかもしれませんね。」
あると思います。笑 (´_ゝ`)天津木村か。
「お金と欲」について僕もちょうど書きたいな~と思っていたので、笑 今書いている浄化のお話がひと段落したらまた書いてみます。